どうも、ししくらです。
本ブログは勉強したり読んだ本の内容をまとめたりを進めていくつもりなのですが、ここの開設に先駆けて古典の勉強をしてぇな!(唐突)ってことがあったので、一冊本を買っておりました。
ちょうどよいので、最初はこの本で勉強した内容でも書いていきたいと思います。
何故古典のことを調べたかすら定かではないのですが、なんかいい感じのこと言っているどこかの教授をWeb上で発見して、その人が本出してるやんけ!買ったろ!!ってテンションで購入していました。勢いって大事。
得てしてこういう勢いで始めた勉強は面白かったりするので頑張っていきましょう。千円以上出してそのままにしておくのももったいないですしね。
古典の基礎的な部分を抑える
早速ですが、自分はバリバリの文系で大学もそっち専攻だったため、一応古文をよく知っているべき人間でした。しかし正直なところ受験期に古文単語の勉強をちょっとやって以来ほぼ全く触れておらず、おおまかな内容すら完全に忘れているというのが現状です。
そのため、些細なことにも結構勉強になるわ!と反応してしまう可能性が高いです、いないとは思いますが高レベルな読者諸兄におきましては適当にドラッガーでも読んでいい感じに知識欲求を満たしておいてくれたらと思います。
そもそも「何故古典の勉強をしないといけないのか」ということを友だちと話していたのがきっかけで勉強する気になった覚えがないでもないのですが、古典に関しては昔からあんまりにも自分の身になっていなかったため、一回学びなおしたいと考えていたこともまた事実でありました。
というわけで、何かの折に無知を晒さない程度には学んでいきたいと思います。
一応高校で必修の内容だったわけなので、まあ常識の範囲として知っておいたほうが無難でしょうってことで。
では行ってみましょう。
参考として買った本
Webの知識だけで体系的に知識を学んでいくのは基本無理だ、という持論を持っているため、とりあえず本を買ったことを後悔しないで済みそうです。
買った本はこちら「大学生のための文学トレーニング 古典編」
詳細はAmazonさんに任せます。
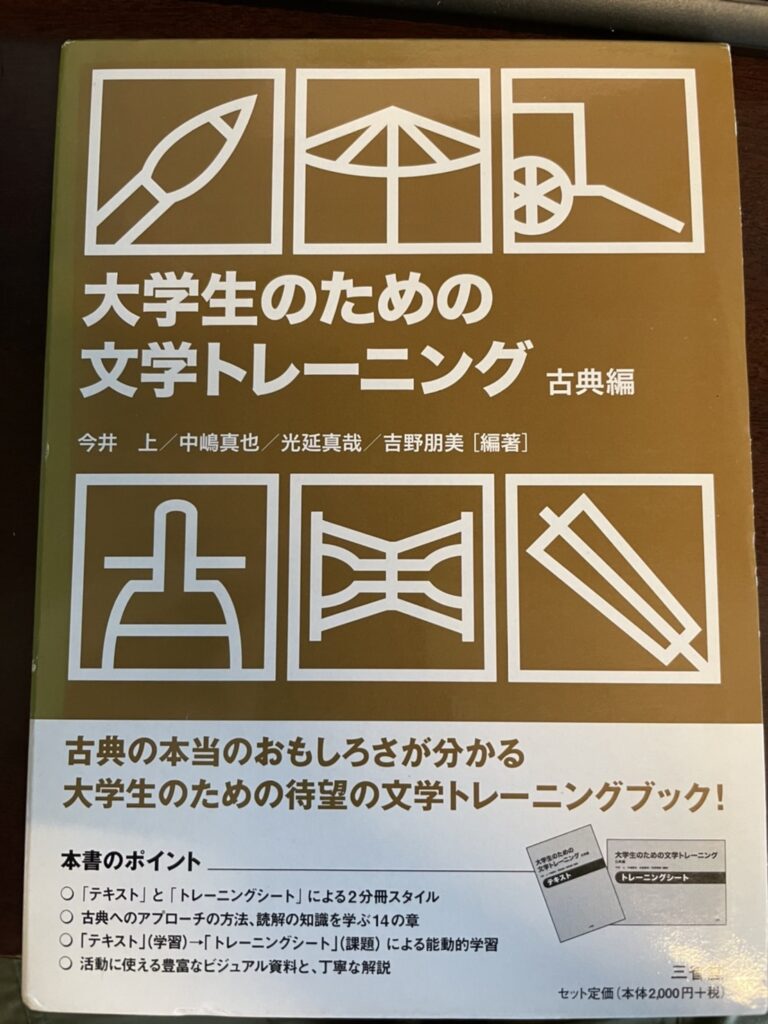
内容とか何も調べないで買ったのですが、2013年と結構古い本なんですね。
まあ古典の勉強なので古くても別に問題ないのですが。
何が良いって、表紙のところに「古典の本当のおもしろさがわかる」って書いてあったところですよね。普段頭を使っていない人間にとってはわかりやすければわかりやすい文句ほど響くので。
探せばもう少しライトで安いのとかもみつかったかもしれませんが、直感でこちらと相成りました。
早速読んでみます。
「はじめに」から重要そうなことが書いてある
わたしは本を読むときにはじめにからしっかり読んでいくタイプなのですが、功を奏しました。
というのもこの「はじめに」、今となっては全く意識していなかったな、という古文勉強における基礎的で重要なことが書いてありました。
古典文学は、江戸時代に出版が普及するまで、書写され受け継がれ行くものでした。
大学生のための文学トレーニング 古典編 はじめに p.2
(中略)その作品を読むために、どの本文を選ぶか、そして本来のあるべきテキストを制作していくこと、これらが実は古典文学を学ぶ上での究極的な基礎作業なのです。
そう、古典作品は書き写して伝わってきたもののため、本文が変わっていってしかるべきものなのだ、ってことです。
もしかすると古文の授業の一回目等で習う内容なのかもしれないが、わたしは残念ながら一ミリも覚えていなかったため、そう言われてみればそういうものだよな、といった感想をもったわけですね。
このように、知っていて当然という内容をしょっぱなからしっかりカマしてくれるのは不勉強な人間にはありがたいことです。知ってる人なら当然とスルーし、知らなかった人はこの時点で知識として得られますので。
というわけで早速学びをひとつ得た勢いそのまま、最初のセクションである「文学作品のさまざまな貌」へと進みましょう。
文学作品のさまざまな貌 『伊勢物語』
この段は早速、さきほど知った「多くの人によって写されてきたことで、少しずつ違った物語が出来上がってきた」という部分の違いを学べるようです。
これセクション内の内容全部書いていくとめちゃくちゃな分量になるので、物語ひとつ、区切り1つ分ごとに記事としていきましょう。
まずは伊勢物語からみたいですね。
うん、名前は知ってる。
伊勢物語ってなんなのさ
伊勢物語は、本によって異なるがだいたい125段前後の小さな章段が集まった歌物語だそうです。
で、その中でも核と言える章段があるそうで。
そこを抑えると理解するのに良いって書いてます。
ここのところのわたしは相当の無勉強野郎だったので、伊勢物語がいつの作品すら覚えていませんでした。ググってみれば速攻でてくることって記憶に残りづらいですよね。で、調べてみたところ平安時代のものだそうで。あまりにも当たり前のことらしくて本に書いてなかったんですよね。
Wikipediaには他にも大層なことが書いてありまして、「『竹取物語』と並ぶ創成期の仮名文学の代表作」「現存する日本の歌物語中最古の作品」「『源氏物語』と双璧」「『古今和歌集』を加えて同時代の三大文学と見ることもできる。」などなど、べた褒めでした。よく話きくだけのことはあらぁ。
作品としては「ある男の元服から死ぬまでをまとめた話」ってまとめてしまうとわかりやすそうです。そう言われてみれば、まあそんなに難しいものじゃないんだなぁとわかります。
六十九段「伊勢の斎宮との恋」
伊勢物語を理解する上で核にあたる章段、ここに出てくる六十九段がその1つなのだとか。
「伊勢の斎宮」との儚い契りを描いた段だそうなのですが、わたしが読んだ上でめちゃくちゃ要約するとこんな感じですね。
ある男が狩りの使いで伊勢の国にいったとき、「伊勢の斎宮」に会った
男が誘うと夜に来てくれたのだが、ろくに話しもしない内にすぐ帰ってしまい、男はへこんだ
へこんでいると、女から「昨日会ったのは夢だったのか現実だったのか?」的な歌が届く(メンヘラ?)
男は「もう一度会いましょう」と歌を返したが、その晩は別の宴会があって、結局会えずしまいだった
夜が明けそうなところ、女は盃を置く皿に下の句の無い歌(浅い縁でした)を書いてよこした
男は下の句(ともに逢瀬を持ちましょう)と返し、尾張国にかえった
いやぁ、古文ガチ勢に助走つけて殴られても文句言えないレベルなのですが、まあ完璧は求めていないのでこんなものでひとまずいいでしょう。
男女が会いたい、でも会えない、切ない別れ、的なことと理解すればよいんでしょうか。これ大体でも良いから当ってるかがわからねぇから困るな。
内容に関しては深く解説されていなかったのですが、伊勢斎宮が神事に絡むなかなか特殊なポジションで、男は結構頑張ってその恋に挑んだっぽいですね。その辺が一括に「主人公の面目が躍如としています」と書かれておりました。
そのへんもう少し詳しく知りたい気もしますが、このテキストではこれ以上はわからなそうです。
なんで核となるのか、ちょっとググってみたくらいではわからなかったので、まあ今回に関してはこんなところが限界でしょう。
さまざまな貌 って点は?
さて、「文学作品のさまざまな貌」と謳ってる章であるため、載っていた文と他の文を比較することになるかと思うのですが、何と比較するのでしょう。
するとなんと、この伊勢物語、仮名で書かれた話なのに全部漢字にした人がいるらしいんですね。
それと比べてみましょうってことでした。
いやぁ、これに関しては全くわからんのでスルーしました、漢字の並びを読めるようになる勉強をしたいわけじゃないんすわ…
そも、「書き間違えや解釈の違いで出来た別の文と、漢字に変換した文とは完全に別レベルの話では?」って思っちゃったのもありますよね。
そりゃあ同じ内容を別の文体で書いてるので広義ではそりゃ「さまざまな貌」って言ってもいいかもしれないけれど、これは違うのでは?古文の文同士でその違い示して欲しいところじゃん?と内なるクレーマーが文句言い始めてしまったのでここまでにしておきます。
この章段の元ネタが中国唐代に書かれた「鶯々伝(おうおうでん)」だとか書かれても、あ、そっすかってしかなりませんでした。
もしかして、わたしの古文学習適正、低すぎ…!?
ってなりましたが、まあふわっと学習できればとりあえず良いので、こんな感じでゆるくやっていきましょう。
総括
なんか最初からちょっと作者の意図したことを意図した形で学べていない気もしましたが、まあ古典の勉強といっても常識っぽい部分を把握してぇな、くらいのゆるい感じなんで、さらりとやっていきましょう。
本体のテキストとは別に、別冊のトレーニングシートが付いていたのですが、この問題はやらなくてよいかな、ってなってます。文法とかなんですもの…模範解答とかも無いし、そもそもそのへんの知識なにもテキストに載せてないのに問題出さないでくださいよ、と。
大学生のための、って書いてあるのはそういうことか、とちょっとだけ後悔しました。
大学生に買わせる本ってこういう講義でカバーしてね、みたいな部分結構あるよなって思い出したり、といったところです。
とりあえず、万一これをみた古典つよつよの民の方は、何故伊勢物語は六十九段が核と呼べるのかを教えていただけると幸いです。
初っ端から他力本願で大丈夫だろうか。
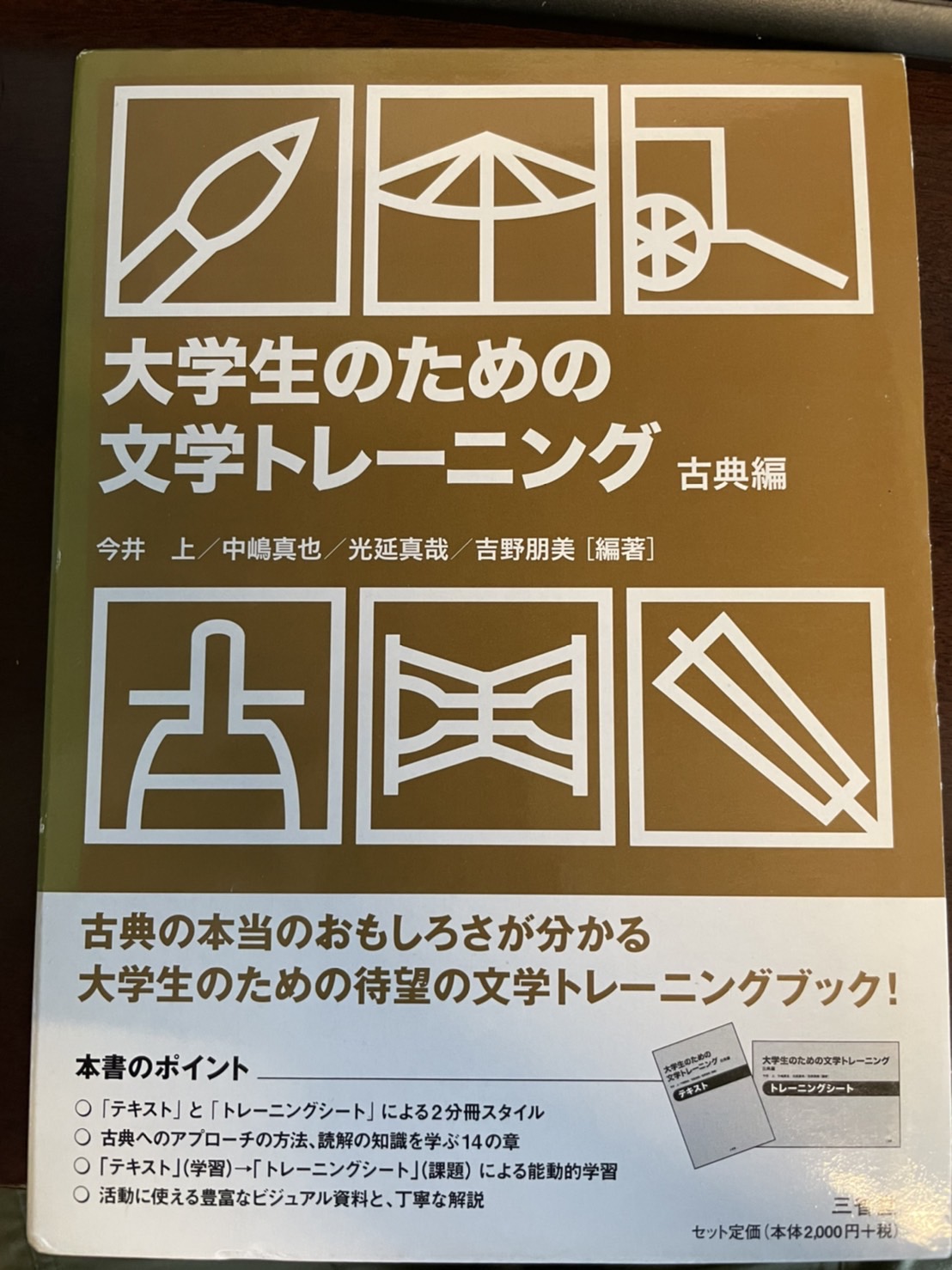
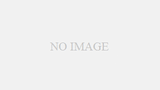

コメント